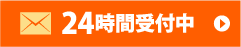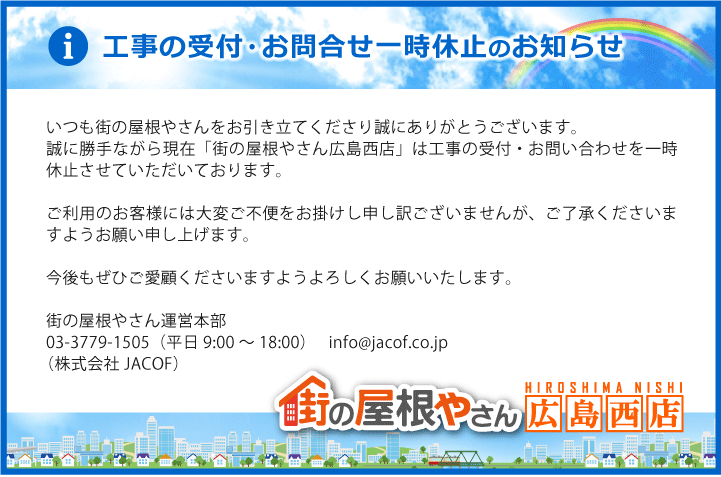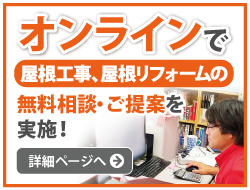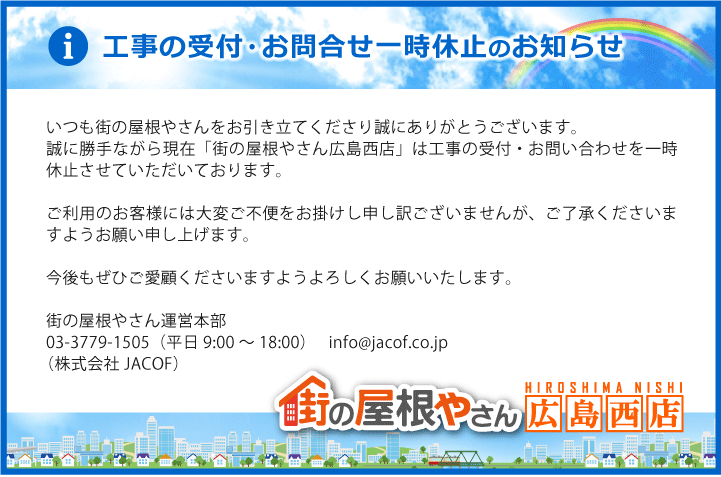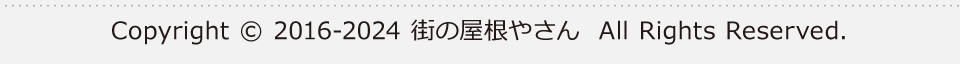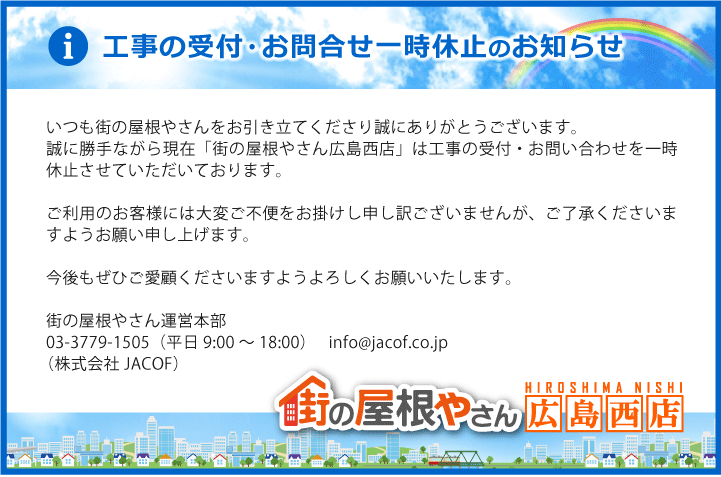
のし瓦って何?どこの部分なのか、役割は何なのかをご紹介
このブログでも度々登場してくる「のし瓦」。今回は、こののし瓦がどこの部分で、どういう役割があるのかを記載したいと思います。
 ブログを見て頂いたことがある方はご存知だと思いますが、のし瓦がどこの部分かというと、屋根の棟瓦の下、細長く見えている瓦のことをいいます。
ブログを見て頂いたことがある方はご存知だと思いますが、のし瓦がどこの部分かというと、屋根の棟瓦の下、細長く見えている瓦のことをいいます。のし瓦を並べた際の継ぎ目の部分ですが、雨水が侵入してきやすく、漆喰や赤土が水を含んでしまいます。のし瓦の継ぎ目をずらし積み重ねることで雨水の進入を防ぐことができ、重ねれば重ねるほどより防ぐことができます。
また屋根の装飾やデザイン性の意味合いでも枚数を変えているみたいです。
 見えている部分が少ないのですが、実際はこのような長方形の形をしています。これ以外の形・デザインも様々あります。
見えている部分が少ないのですが、実際はこのような長方形の形をしています。これ以外の形・デザインも様々あります。また瓦割りの瓦はのし瓦を使用されています。のし瓦は1枚を2枚に割って使うため、裏面に割りやすいよう細い溝があります。何枚も重なると難しいかもしれませんが、1枚2枚なら、瓦割り出来そうですね。
のし瓦に注目して屋根を観察するのも面白そうです。
9時~18時まで受付中!
03-3779-1505